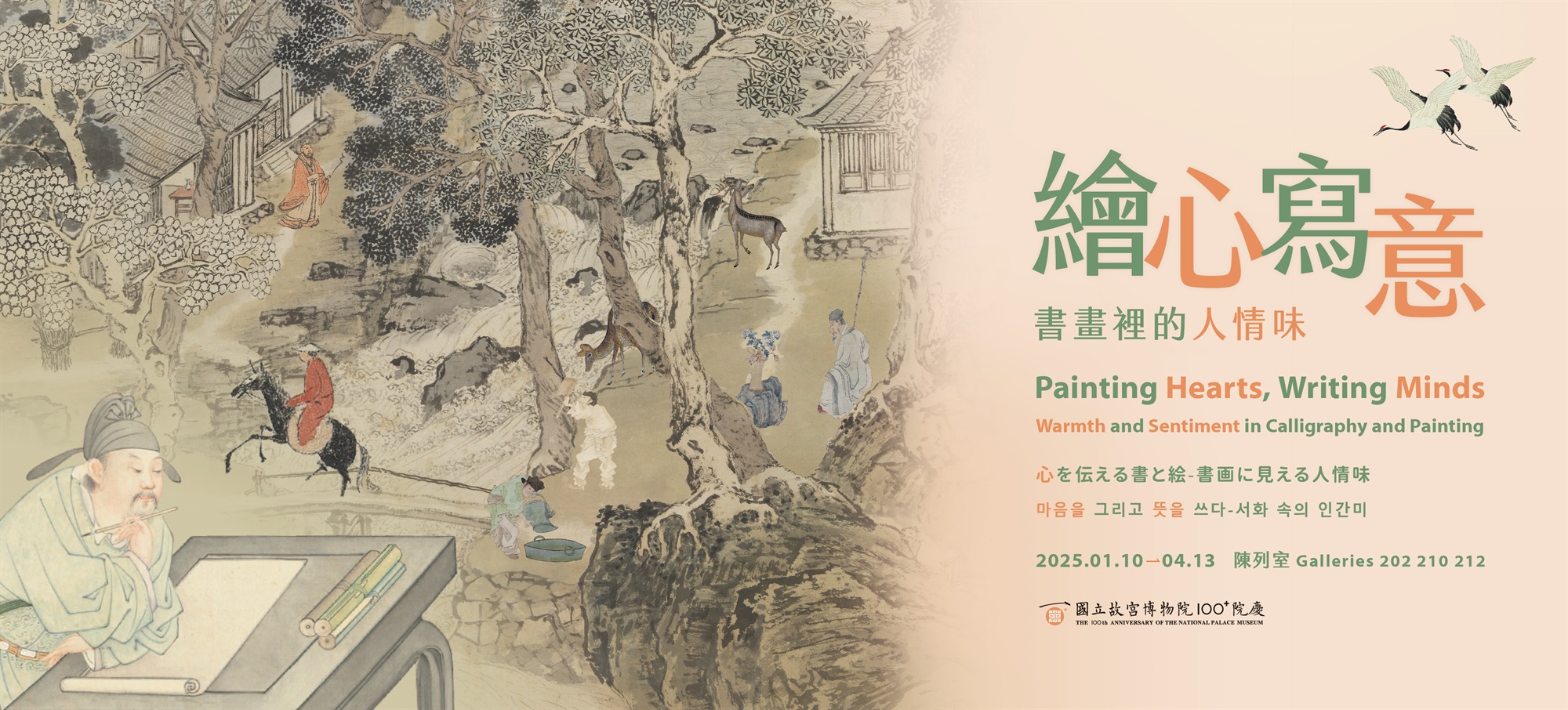長寿を祝う
-
明 沈周 廬山高
故畫884
紙本
国宝沈周(1427-1509)が師である陳寛の70歳の大寿を祝うために贈った作品で、聳え立つ廬山の高大さを借りて、師の徳行を讃えている。
群山と渓谷が描かれており、遠方まで連なる山々が雲気に覆われている。中景は山体が隙間無く重なり、その左側には滝が流れ落ちている。中央に斜めに聳える岩壁があり、上部に余白が残されている。側面は僅かに着色され、後方の山石とともに空間に奥行きを生み出している。全体に元代の王蒙(1308-1385)の画風を用いて複雑かつ律動感のある筆致で山石の質感が描かれており、生気溢れる画面となっている。下方の岸辺に一人の人物が佇んでおり、ごく小さな姿によって山体の高大さが際立って見える。山水の風景と長篇の題詩によって、師への敬慕の念が表現されている。
-
明 項元汴 倣蘇軾寿星竹
故畫569
紙本項元汴(1525-1590)、字は子京、号は墨林居士、明代の著名な収蔵家で、書画鑑賞に精通していた。この作品は友人の求めに応じ、その父の誕生祝いのために描いた絵である。この絵には、斜面の岩の傍らに生える2本の細い竹が描かれており、濃淡異なる竹が互いに映えている。岩は荒々しいが、竹は繊細な筆致で描いてあり、異なる筆法で物象の特質が表現されている。
題識には、この作品は蘇軾から発想を得たと記されている。蘇軾(1037-1101)は杭州の寿星院へ旅をしたことがあり、後に黄州に左遷されていた頃(1080-1084)に、その竹林の風景を懐かしんで詩を詠んだ。それから何年か後(1090)にその詩を通悟禅師に贈った。絵を贈られた人物は禅宗を篤く信仰していたため、この絵のイメージはその趣味志向にふさわしい。
-
清 徐揚 赤松黄石二仙図
中畫191
紙本徐揚(1712-1777以降)、江蘇蘇州の人。乾隆16年(1751)に乾隆帝が初めての南巡で蘇州を訪れた際に徐揚がこの画冊を献上した。それにより宮廷に仕えることになったという。
赤松子と黄石公は伝説の仙人。劉向の『列仙伝』には、「赤松子は神農の時代の雨神である。」とあり、雨を司る長生の神だとしている。司馬遷の『史記・留侯世家』には、黄石公が下邳(現在の江蘇省邳州)の橋の上で、張良に兵法を伝授した故事が記されている。この絵に描かれた赤い松と黄色い岩、青々とした竹の色遣いは清麗で、配置に奥行きが感じられる。すっくと聳える松の木から1本の枝が斜めに伸びており、下方の竹と岩石に調和している。画上の款題を見ると、乾隆帝の誕生祝いのために描かれた作品だとわかる。
-
清 黄鉞 寿世徴祥冊 南山同寿
故畫3359-9
絹本黄鉞(1750-1841)、乾隆朝から嘉慶朝、道光朝に仕えた。山水画や花卉画、市井の暮らしぶりを描いた風景画を得意とした。この作品は『寿世徴祥』(画冊)に収録されている。嘉慶帝の子である愛新覚羅綿愷(1795-1838)が祝詞を書き加えている。君主の長寿(或いは誕生日)を祝い、国運の隆盛を願った作品。
この作品は『詩経・小雅・天保』の「南山之寿」が引用されている。臣下が君主の長寿を祝った詩歌で、「南山」は終南山(現在の陝西省に位置する秦嶺山脈の一部)を指すものかもしれない。左側の近景には松の木と岩石が重なっており、その平地に佇む人物が遠方の高山に向かって拱手している。ごく小さな身体と高山が鮮明な対比をなしており、険しい山の高大さが際立って見える。