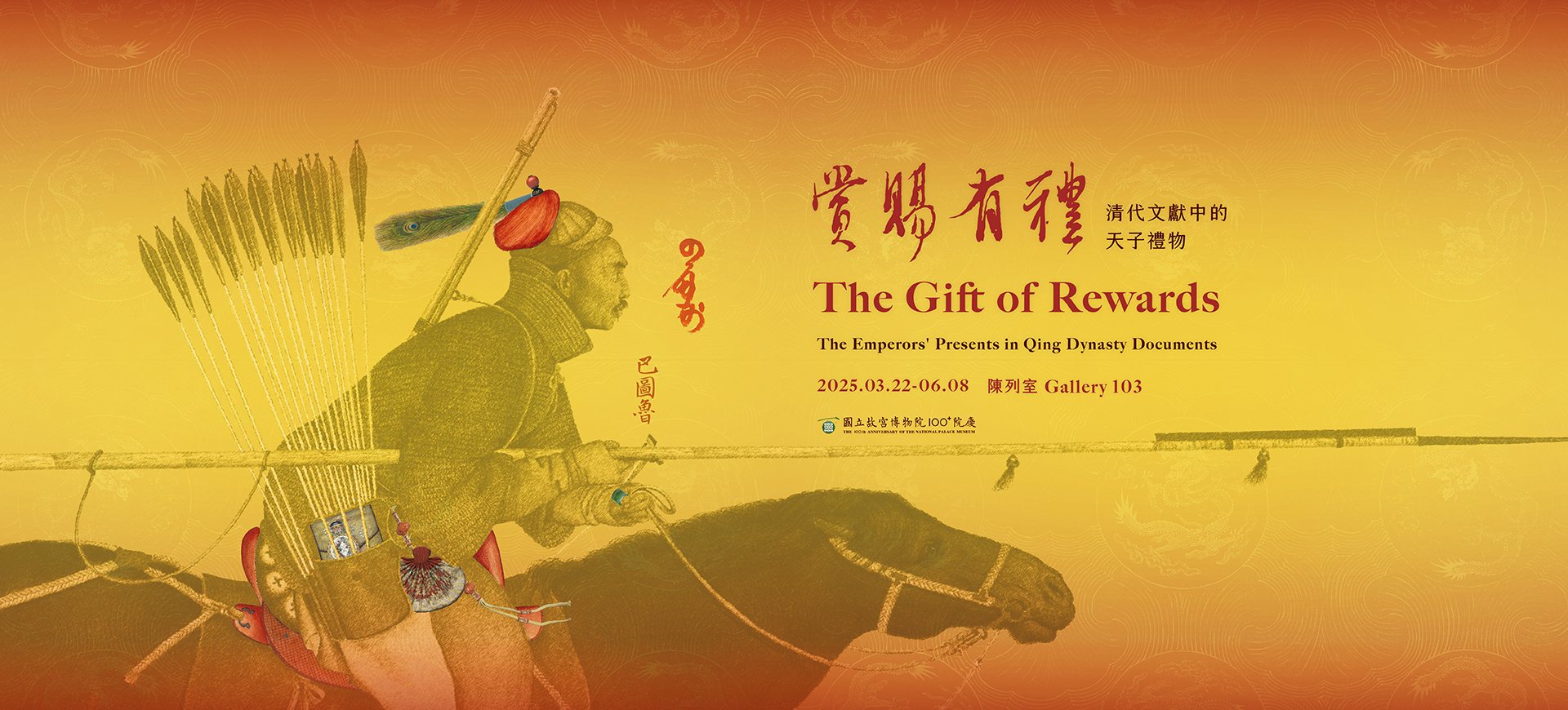礼は何処から来たのか
清帝国の時代になると、場所が塞外(中国北方、万里の長城の外側)であれ、朝廷であれ、途切れることなく褒賞品の授与が行われました。当初、努爾哈斉(ヌルハチ,1559-1626)は主に草原の物を下賜していましたが、朝廷の制度が確立されると、賞賜の種類も多様化し、服飾品の頂戴や花翎、官位や称号などのほか、皇帝の食べ物や食器類、書籍や銀両など、多岐にわたりました。
しかし、皆さんはこの賞賜の背景について考えたことがあるでしょうか。それらの褒賞品は宮廷内のどの機関と関わりがあったのでしょうか。それについてもご紹介しましょう。
-
恩威並行─ヌルハチの奨励策
大清太祖高皇帝実録
大紅綾漢文本
故官001536-001538清史によれば、後金の初代ハーンであるヌルハチ(努爾哈斉,1559-162)は、入関前から軍事面において「恩威並行」と言える管理体制を敷いており、従順な者に対しては徳をもって人を服し、逆らう者には兵を出した。そのため、「功臣を厚遇する」ことを重要な国策としたほか、自ら進んで遠方から帰順した者にも手厚く恩賞を与えていた。
書中の記述によれば、1619年(天命4年,明万暦47年)3月に、明軍との最初の決戦が行われ、サルフ(薩爾滸)で大勝利を収めた後、秋の7月に後金の大軍が遼東の軍事上の要衝だった開原に再び進攻すると、瞬く間に鉄嶺を占領して勝利した。その時、開原の千総だった王一屏らは兵を連れて投降した。
ヌルハチは大いに喜び、守備の阿布図のほか、6名の千総、守堡、百総などの官に多くの褒美を与えた。人や牛馬、羊、駝、白金、幣及び布地など、満州族の伝統に則ったもので、数量は位階の高低により違いがあった。 -
礼尚往来─ホンタイジとホルチン国大妃
大清太宗文皇帝実録
小紅綾本ヌルハチの第8子のホンタイジ(皇太極,1592-1643)は後金の第2代ハーンで、清を開国した皇帝でもある。『大清太宗文皇帝実録』には、清朝成立前後のホンタイジの政治活動についての記述があり、後世の人々が清代初頭における施政について知るための貴重な資料となっている。
本書によれば、1629年6月10日(天聡3年閏4月19日)に、中宮皇后孝端文皇后ボルジギト・ジェルジェル(博爾済吉特・哲哲,1599-1649)の母親であるホルチン(科爾沁)国大妃が来訪した際、ホンタイジは三大ベイレ(貝勒)及び大勢のベイレの妃たちを率いて出迎えたという。
この訪問で大妃は大量の贈り物を持参した。貂裘や貂套(貂の毛皮製の服)、金仏頂貂冠、金鞓帶(ベルト)、手帕(ハンカチ)、合包全副(一揃いの小袋)、朝衣、鞾(靴)、金仏頂涼冠などのほか、ヌルハチが関外で駱駝や牛馬、羊などの貴重な財産を褒美として与えていた、満州族の伝統に沿った贈り物もあったという。 -
清代初期における賞賜の等級と制度
国朝宮史
清 于敏中等奉敕撰
清乾隆三十四年(1769)内府朱絲欄写本
故觀003449本書には早くも1677年(康熙16年)には規定があり、宮殿内の各所で賞賜された者は必ずそれを登記せねばならず、褒美を授かった者の氏名及びその年月日が明確に記録され、もし事実に反する記述があれば、重く罰せられた。
このほか、1744年(乾隆9年)に賜宴及び賞賜を与えられた大学士も等級分けされており、重用されたオルタイ(鄂爾泰)と張廷玉はいずれも頭等(最上位)の大学士とされ、もともとの賞賜のほかに如意1本と寧紬(絹織物)1疋、茶葉1瓶も下賜されている。武英殿から持ち出された賞賜書籍『楽善堂全集』及び『性理精義』は各165部もあり、当時、宴に出席した頭等から五等までの大学士が165名いたことが知れる。