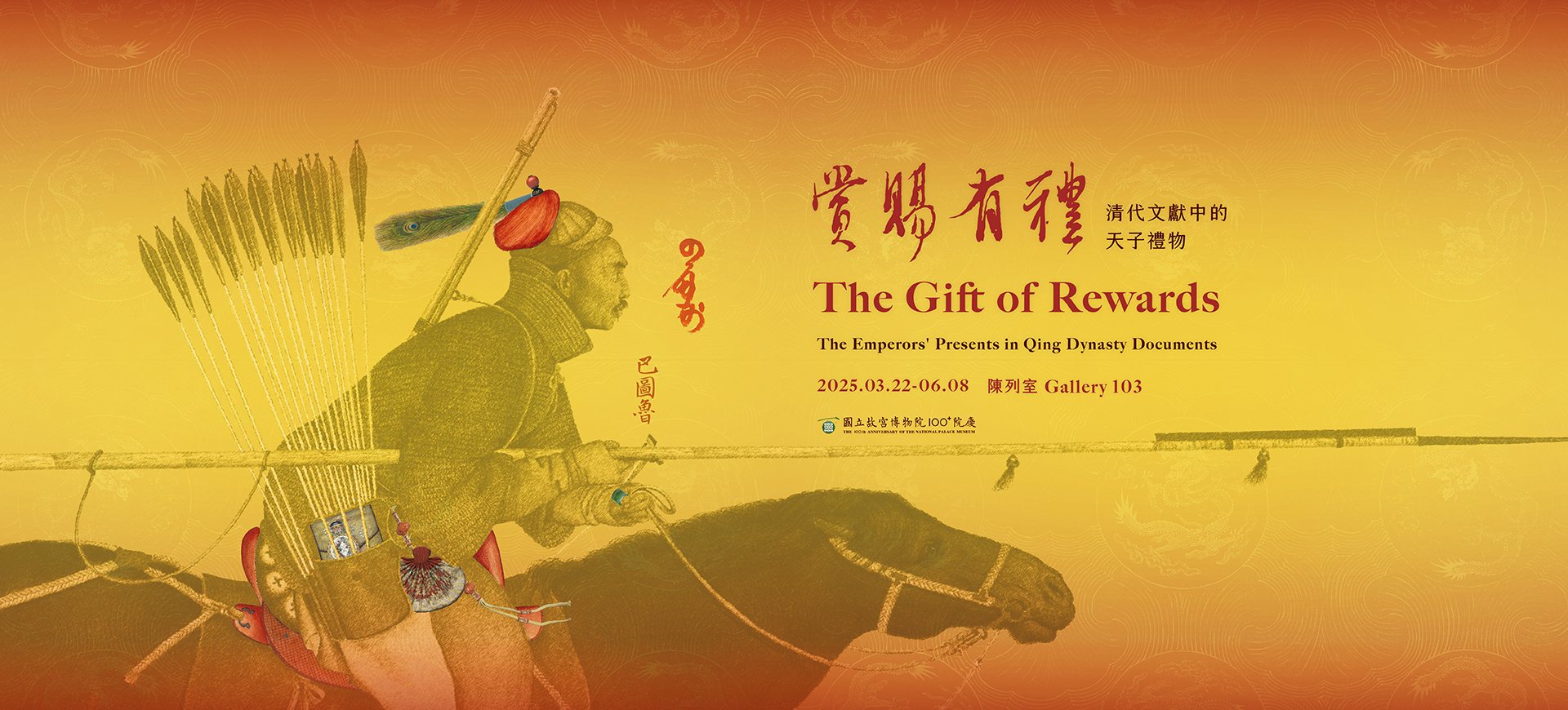昇進と昇給
皇帝からの褒賞は品物だけではありませんでした。地位や名声を高める加官や爵位、称号、肩書きの授与のほか、頂載や花翎、黄馬褂などの服飾品、勲章贈与などが、官吏たちの仕事の場でよく授けられる贈り物でした。
賞賜には様々な種類があり、皇帝たちは時と場合によって使い分けていました。この褒賞制度は康熙朝と雍正朝で徐々に形成されました。昇進及び封爵に関しては、乾隆朝から光緒朝まで、外交上の必要から互いに宝星(勲章)を贈り合うようになり、それが次第に慣例となりました。栄誉や名声を象徴する非物質的な贈り物は品物より遙かに価値のあるものでした。
功牌─軍功と栄誉の証
-
光緒紙質功牌
光緒紙質功牌
光緒十一年十一月二十三日
国立歴史博物館蔵 10032「功牌」とは、古代において軍功のあった者に与えられた獎牌(記章の一種)である。明朝が用いていた銀製の功牌は今日の「勲章」のようなもので、「賞」という文字が見える。清朝になると、紙製の功牌に改められ、「賞状」に近いものとなった。
この功牌(国立歴史博物館蔵)は紙製で、「功牌」と書かれている。雲南で軍務にあたっていた湖南提督一等子爵鮑超(1828-1886)は、文童(儒童とも言う。まだ童試を受験していない童生)陳元曽が雲南霑益州の行営で多大な貢献をしたので、褒美として陳元に「八品頂戴」のほか、「功牌」も授けてくれるよう光緒帝に奏請した。「功牌」を拝受することは栄誉の象徴であり、一般的にはそれと同時に別の官名や銀両も与えられ、一種の昇進昇級の機会でもあった。
官位を示す頂珠─清代官員の帽子から知る等級の違い
「頂戴」とは、清代官員が朝服や吉服、常服を着る時にかぶる帽子の上部につけた、宝石などをはめ込んだ「頂珠」のことで、等級によって、冠頂につける宝石も異なっていた。清代初期は一品官員はルビー、二品官員は珊瑚、三品官員はサファイヤ、四品官員はラピスラズリ、五品官員は水晶、六品官員は硨磲(シャコ貝)、七品官員は純金、八品官員は陰紋縷花金、九品官員は陽紋縷花金、無官品者の帽子には頂珠がなかった。
雍正年間になると、三品から六品官員の頂珠は宝石の代わりに色の近いガラスが使われるようになったほか、牙骨を染めて宝石や珊瑚の代わりに使用していた。
翎管と花翎─官帽へのこだわりもいろいろ
この奏摺には、皇帝から賜った翎子や薬錠、翎管、孔雀翎、琺瑯鼻煙壺、玳瑁火鎌袋、克食などについて触れている。「克食」とは、宮廷の御膳に並ぶ食べ物のことで、「翎子」と「翎管」、「孔雀翎」は清代官員の帽子につけた装飾品である。
官員の冠頂につけた装飾品は頂載のほか、翎管と花翎があった。「翎管」は長さ約6、7cmで、素材は玉もあれば、翡翠や琺瑯、磁器など様々で、翎子を挿すのに使われた。「翎子」は官員の帽子の後ろに垂らす羽根のことで、主に皇帝から功績のあった官員に下賜された。頂戴と花翎は清代官員の地位を象徴的に示すものとみなされる。清朝宮廷を舞台にしたテレビドラマや映画では、官員が何か過ちを犯すと官位を失い、罰として皇帝に「頂戴花翎」をむしり取られる場面がある。
「翎子」には「藍翎」と「花翎」の2種類がある。「藍翎」は鶡雞(ミミキジ)の羽根で、一般的には六品以下の比較的身分の低い官員か侍衛に下賜された。「花翎」は五品以上の高官か勇士に与えられた。孔雀の羽根を使ったものなので、「孔雀翎」とも言われる。
清の時代、孔雀の羽根は入手困難だったため、至高の恩寵と栄誉の象徴だった。また、孔雀翎の尾羽根には目玉のような斑紋があり、単眼と両眼、三眼に分類されていた。孔雀の眼が多ければ多いほど、功績の大きさを示しており、下賜された翎子が三眼花翎であれば、最も尊く名誉ある地位の象徴だった。
御賜双龍宝星─清朝晩期の栄誉と西洋式勲章の融合
1882年2月7日(光緒7年12月19日)、総理各国事務衙門奕訢(1833-1898)が皇帝に「御賜双龍宝星」のデザイン及び等級分け、これらに関する規範制定への同意を求めて奏請した。「宝星」には双龍が彫刻されていることから、「双龍宝星」と名付けられた。
「双龍」は皇権の象徴であり、初期は等級が頭等から三等に分けられ、各等がまた三級に分けられていた。宝星は金や銀、琺瑯、カラフルな宝石で装飾され、その尊さが強調された。周囲は放射状に広がる星芒に囲まれているか、八角または十六角星形になっていた。20世紀初期になると、等級が更に細分化され、五等十一級になった。
この「御賜双龍宝星」(国立歴史博物館蔵)は、周囲に十六本の星芒があり、満州語と漢語による「御賜双龍宝星」6文字がある。上部に小さな赤い珊瑚、中ほどに大粒のラピスラズリ、緑色の琺瑯で作られた双龍がその周囲に配されている。この様式は第四等宝星で、功績のあった武官か兵士に贈られたものである。双龍宝星のデザインは中国の伝統文化と西洋の勲章の作風が融合したものだが、この勲章制度が実施されたのはわずか数十年で、1911年に清朝が滅亡すると、この勲章制度も廃止された。