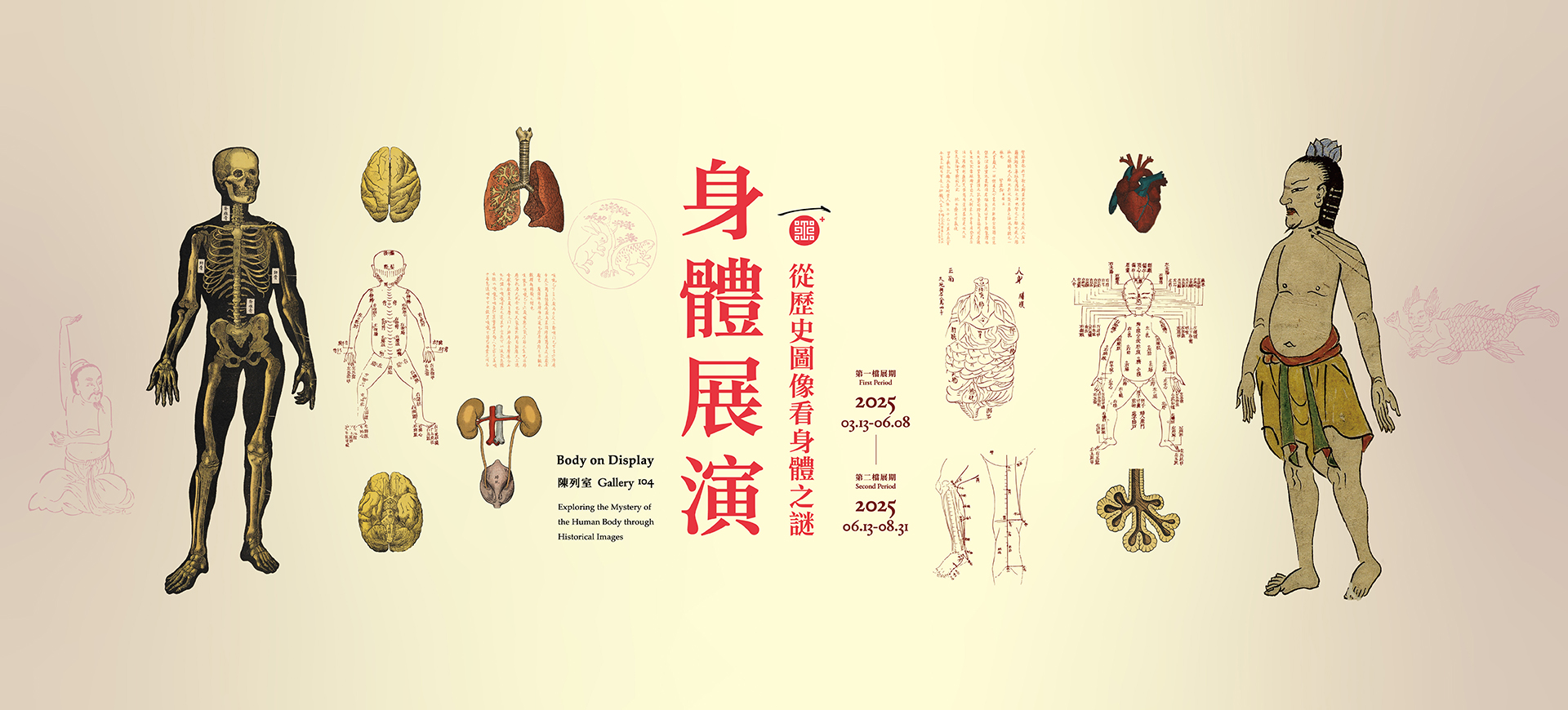身体の規戒
政治権力により規制される身体
政治権力は特定の肢体の動作や儀式を通して身体を馴れさせ、規則に服従するようにし、権力を伝達する道具とすることがしばしばあります。本展では、占卜に関する書籍『御製新集断易精粋』の卦詩と着色図、一連の「平定伊犁回部図」の中から「凱宴成功諸将士図」を展示します。絵図の中の官員たちは、皇帝を前にして恭しく慎み深い表情を浮かべながら跪いており、権力と階級制度による馴化が象徴的に示されています。このほか、バチカン図書館(Biblioteca Apostolica Vaticana)が所蔵する日本の「文章之祖(Bunsho No Soshi)」に掲載されている版画の画像を展示します。画中に見られる対話の場面を見ると、高位の者が高所に座り、その権力が象徴的に示されています。下位の者は低所で跪いており、肢体の様子で高位者に対する畏敬の念と服従の意思が表現されています。
刑罰と刑具が身体に与えた戒め
統治者或いは司法機関は刑罰や刑具によって人を拘束して痛みを感じさせ、懲罰という目的を達成し、社会秩序と権力の関係を形作りました。例えば、縄や枷、鎖などで行動を制限したり、肉刑で身体に損傷を与えたりしたほか、皮膚に烙印を押す刑もありました。一部の刑具は変化しながら現代に至り、民俗活動の一環にもなっています。一例を挙げると、嘉義城隍廟の祈福儀式と東港迎王平安祭典では、消災厄除け、招福を願って枷をはめた人たちの姿をよく見かけます。しかし、現代の宗教活動では紙製の枷が使われており、祭りが終わりに近づくと燃やしてしまいます。燃える枷とともに罪過も消え、業障もまた消滅すると言われています。
礼教秩序による身体の束縛
-
『新編纂図増類群書類要事林広記』
(元至順間建安椿荘書院刊本)
「習义手図」と「習祗揖図」
(宋)陳元靚撰
故善004363-004374中国の伝統的儀礼の行い方は多種多様で、対象によって動作にも違いが見られます。儀礼を行う時の動作には規則があり、姿勢や態度も制約を受け、身体的な自由が制限される中、礼制の秩序と身分の尊卑が示されます。『新編纂図増類群書類要事林広記』には、様々な面会に際しての礼儀が詳しく記されており、場面ごとの動作についても説明されています。例えば、「义手」(「叉」とも書く。年少者及び低位の者から年長者及び高位の者に対しての礼)、祗揖(両手を合わせての礼)、展拝(跪いての礼)などがあります。これらの礼儀は長期にわたる身体動作の訓練を経て、各個体が日常的行為の中で礼教規範を内在化させることにより、最終的には身体が礼制秩序の一部となっていたのです。