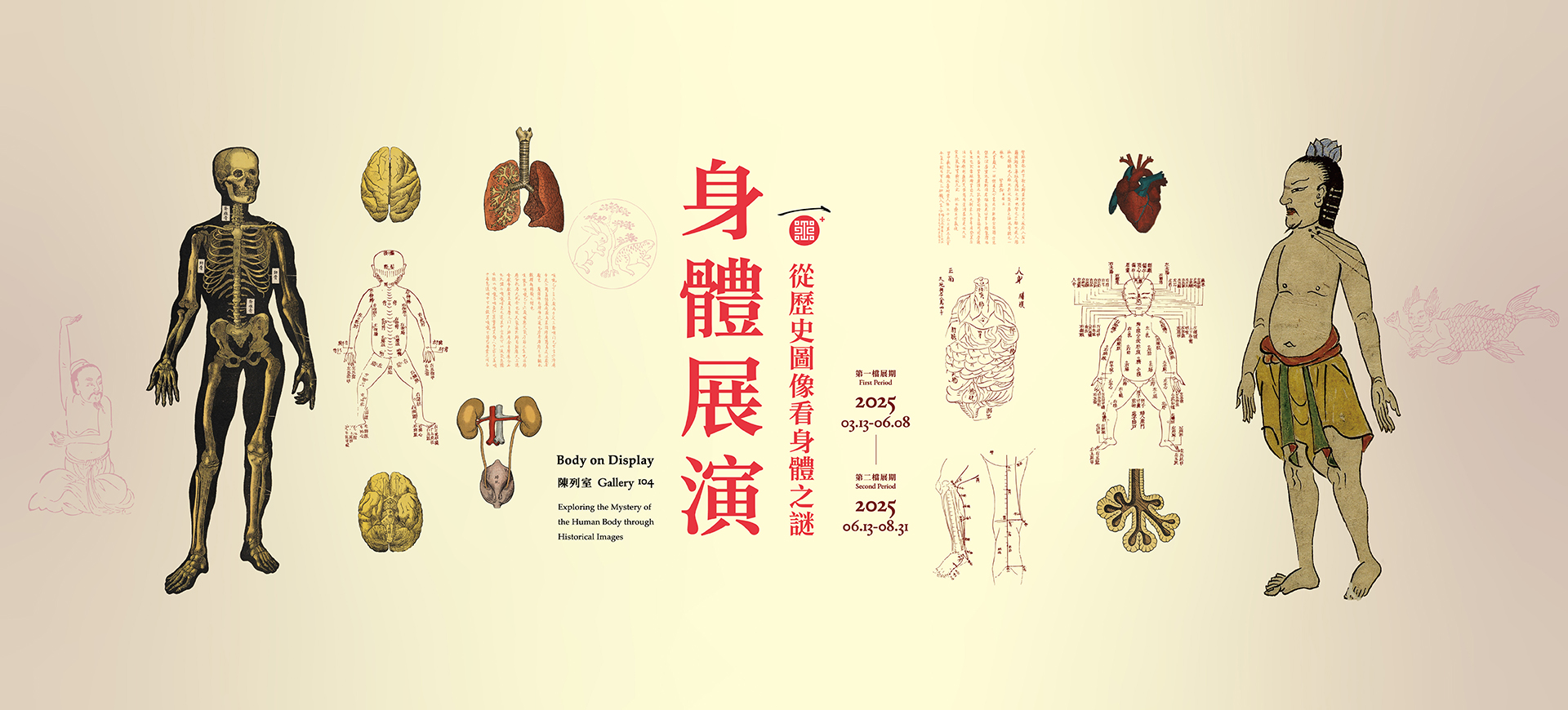身体を見つめる
身体を見つめる
-
「理科掛図」
作画者不詳
(民国8年〔1919〕2月2版上海商務印書館発行)
故獻000001-000048人間 の身体について説明する際、内臓の構造や経絡、ツボの位置、気血などを記すのが中国伝統の記述法です。こちらのコーナーでは、全身の内臓や身体の部分、経脈、鍼灸とツボなどを含む身体の絵図を展示します。例えば、旧題によれば漢代の医者華佗(145頃-208)が著したとされる『玄門脈訣内照図』には、人体の正面と背面などの絵図があります。朝鮮の名医許浚(1546-1615)の著書『東医宝鑑』には五臓六腑図が掲載されています。また、南宋の医学者の著書『鍼灸資生経』には、ツボの位置と鍼の刺し方が紹介してあり、36幅のツボの位置図も付いています。しかし、清代末期になると、西洋科学の影響を受けて身体の描き方に変化が生じました。清末の新しいタイプの学堂で使われた教科書の補助教材──「理科掛図」の身体の描き方は伝統的なものとは異なり、骨格と筋肉、神経の描写が重視されています。
バチカンの医学的人体図
西洋でルネサンスが広まった時期の解剖学者アンドレアス・ヴェサリウス(Andreas Vesalius, 1514-1564)の著書『人体の構造についての七つの書(De Humani Corporis Fabrica Libri Septe)』には非常に細密な身体図の版画があり、それまでの人体構造に関する誤った論点を正した、近代人体解剖学の権威ある書物の一つです。バチカン図書館(Biblioteca Apostolica Vaticana)は本書に加え、イタリアの著名な版画家ジュリオ・ボナソーネ(Giulio Bonasone, c. 1498-1574)が絵を描いた「解剖研究(Studi Anatomici)」も所蔵しています。こちらのコーナーでは、『人体の構造についての七つの書』と「解剖研究」の一部画像を展示し、西洋におけるルネッサンス以降の身体描写法をご紹介し、本院所蔵の身体図と比較しつつ分析します。
医学タンカ
医学タンカの画像
タンカ(唐卡)はチベット語で「Thang Kha」と言い、チベットの巻物に描かれた絵図を指します。タンカの画題は宗教や医学、天文、暦法、歴史的な出来事、神話、動物、植物…など多岐にわたります。今回展示する画像はその一部で、医学に関するタンカのものです。医学的なタンカはチベット語で「sman thang」と言い、中国語は「曼唐」または「門唐」と音訳されています。チベット族の伝統的医学には長い歴史があり、人体の健康と自然との関係を重んじ、人体の構造や人間の生理機能、病変と自然現象が緊密に結び付けられています。チベットの医学タンカは脈絡図と穴位図(ツボの位置)だけでなく、骨格図や人体各器官図、人体解剖図もあります。
*文化部 モンゴル・チベット文化センター提供
法医学の身体観
-
『律例館校正洗冤録』の検骨図と屍図
(清乾隆七年武英殿刊本)
(宋)宋慈撰 (清)律例館校正
故殿009475-009476中国の伝統的法医学(検験学)と伝統的中国医学は同じく人体に焦点を当てたものですが、両者の境界は人間の生死にあります。中国医学の身体図は生前の内臓と精気の循環に着目したもので、法医学は死後に注目し、身体外部や口腔、骨格の描写を重視しており、内蔵にはあまり触れていません。本展では、本院所蔵の『律例館校正洗冤録』に掲載の検骨図や屍図など、法医学の人体図を展示します。『洗冤録』は宋代の提刑官宋慈(1186-1249)が編纂した現存する最早期の、絶大な影響を与えた法医学の専門書です。乾隆帝(在位期間:1736-1795)は乾隆6年(1741)にこの書籍の校閲及び修訂を命じ、その翌年完成した修訂版を広く頒布しました。書名は『律例館校正洗冤録』に改められ、清代における検験学の標準的知識とされ、官員と仵作(現代の法医学者に相当する官吏)の必読書になりました。
仏教と道教の身体観
どの宗教にも身体に対する独自の見解がありますが、それらの観点は宗教色が強く、象徴的な意味を持っています。道教では、身体の各部分はそれぞれ別の神が司ると考えられています。本展では明朝の文献学者王圻(1530-1615)と、その息子の王思義(生没年不詳)が編纂した『三才図会』を展示します。この書籍には肝神や心神、脾神、肺神、腎神など、体内に宿る神のイメージが絵図に描かれています。このほか、紀元前6世紀の名医耆婆(ギバ,生没年不詳)の名を借りて編纂された『耆婆五臓経』には、着色された手描きの人体図が多数あり、五臓が宗教的な象徴性をもって描写されています。これらの絵図は実際の臓器が描かれているわけではなく、一種の宗教的な人体構造図です。『真禅内印頓証虚凝法界金剛智経』には、仏教の密教と道教で用いる符籙の意義を結び付けた、衆生原形図と玉兎日月女身図があり、人体図に関して宗教による多様な解釈が見られます。