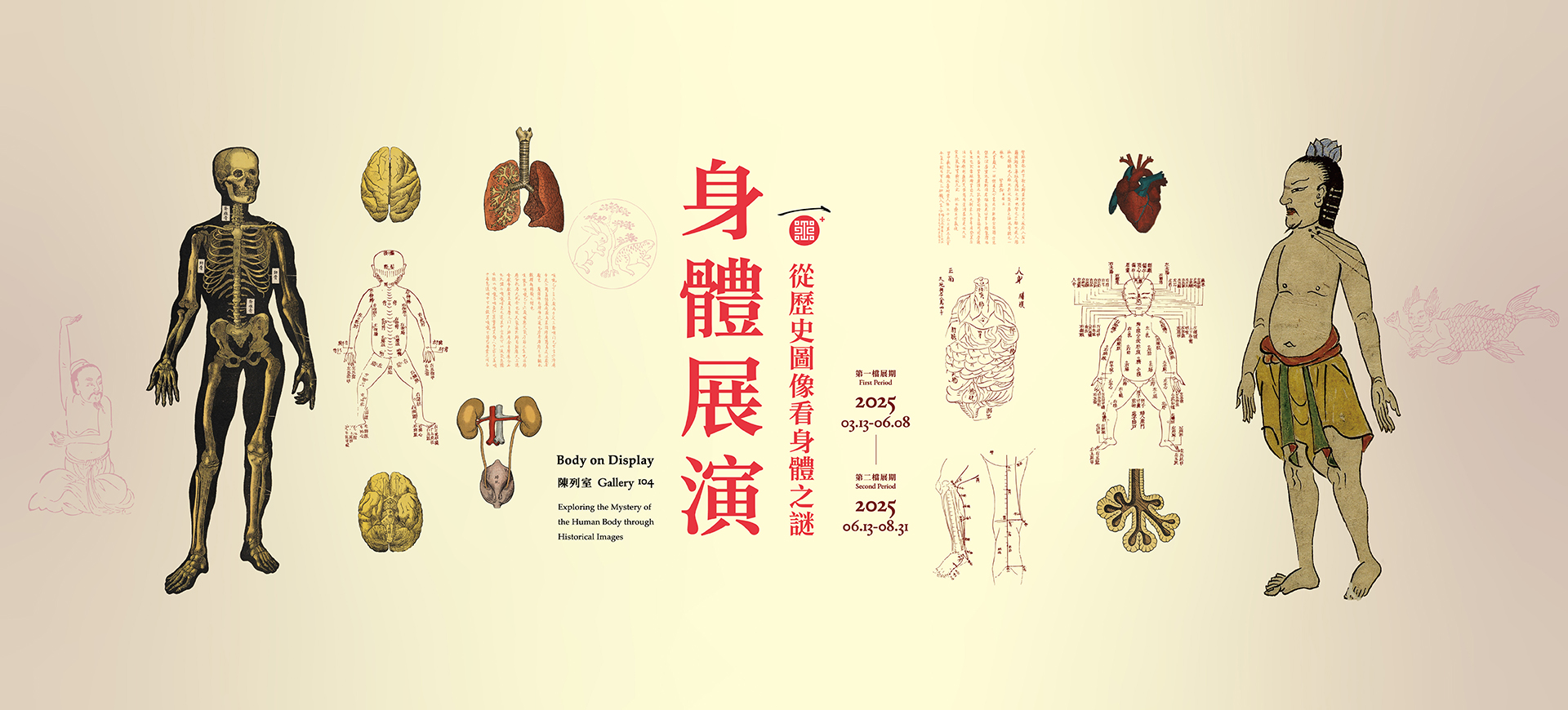身体を鍛える
尚武
古代の人々は国を守るため、或いは身体を鍛えるために武芸の稽古に励み、その動作や価値観を身体的習慣として身につけ、それが特有の身体的特徴を形作っていました。こちらのコーナーでは、『兵録』に見られる様々な拳法や、明代の軍事家戚継光(1528–1588)の著書『紀效新書』で紹介されている武器の持ち方、『少林棍法闡宗』の少林本門棍法について展示します。また、絵画も身体を見せるための大切な媒介の一つです。本展では、イタリアのイエズス会士だった郎世寧(Giuseppe Castiglione,1688–1766)が描いた「阿玉錫持矛盪寇図」を展示します。阿玉錫(Kalmouk Ayusi)が準噶爾(ジュンガル)の汗達瓦齊(ダワチ)(?-1759)で勃発した叛乱を平定した際の姿─左手に手綱を持ち、右手に長い矛を握り締め、両足で馬の胴体をしっかりと挟み、全速力で馬を駆る勇姿が描かれています。この絵は陣図や身体鍛錬とも密接な関わりがあります。身体を鍛えることは陣法展開の基礎となるもので、演習では歩陣図の通りに正確に移動することが求められます。今回は『喻子十三種秘書兵衡』の「七星陣」と「步騎兵演練陣図」を展示し、軍事訓練によって兵士の身体感覚と特徴的動作がどのように形成されていったかをご紹介します。
房中術と秘戯図
「房中術」も古代の人々がどのように身体を鍛えていたかが知れるもう一つの視点です。房中術では、男女の性行為での呼吸法や感情の抑制法、様々な言葉の用い方、身体の動かし方などについて説明されています。明代の文人たちの文章や文集、家訓には房中術に関する論述が多く、養生を説く中国医学の本にもこれに関する議論が少なくありません。当時の人々にとって房中術の主な目的は不老長寿で、病気の予防や治療もできると考えられていましたが、それよりも重要だったのが新しい命を宿らせ、子孫を残すことでした。寝室での行為についての絵図や文字による描写は中国古代の書籍に見られるだけでなく、西洋にも幾つかの秘戯図が残されている点は特筆に値します。しかし、17世紀前後の西洋社会では性に関するあらゆる事物は「隠されていた」のです。
男女平等という視点から見るなら、「房事」が男女にとってどのような意味を持つのかを、一歩踏み込んで考えてみる意味があるでしょう。ある研究者によれば、現存する房中術関連の文書は男性の立場から見た房中術で、男性の利益のために女性を男性の修練道具にしており、房中術において男女の関係は対等ではなかったとしています。しかし、別の研究者によれば、明代の房中術に関する文書では、寝室へ向かう時に男女が互いに共鳴していることや、閨房の雰囲気作り、個人的な欲望の節制などが強調されていることから、女性にも自由があり、房事を楽しむことができたとしています。本展では、『筆耕山房弁而釵』や『修真演義』など、中国の古書に見られる房中術に関する描写を抜き出して展示します。このほか、西洋のスナッフボックス(かぎタバコ入れ)の蓋や隠し蓋の秘戯図も合わせて展示し、これらを正面から捉え、健康的な視点から男女の房事についてご紹介します。このような行為と健康維持や自己修養を結び付け、子孫を残し、命を繋いでいくその重要性に焦点を当てます。
導引術
-
『夷門広牘・赤鳳髓』五禽戯
(明万暦間金陵荊山書林刊配)
(明)周履靖編
平圖012489-012490「導引」とは、呼吸吐納(体内の悪い気を吐き出し、新しい気を取り込む呼吸)や身体を伸ばすことを核心とした養生術で、意念を通して動作を導き、そこに呼吸を合わせて気の動きを調整します。導引術の起源は太古にまで遡ることができます。漢代にはすでに流行しており、神仙家や医家から重んじられ、後に修煉法の一つとして道家に継承されました。歴史上有名な導引術には「五禽戯」と「八段錦」があります。「五禽戯」は虎・熊・鹿・猿・鳥の動きを模倣して身体を鍛え、健康増進を目指すもので、『荘子』の「熊経鳥伸」と馬王堆漢墓から出土した導引図を起源としており、華佗(145頃-208)に伝授されてから後、徐々に普及しました。「五禽戯」は豊富な絵図と解説文という形式で、周履靖(1549-1640)の『赤鳳髓』に記載されているとおり、明代になると広く流伝しました。「八段錦」は八段の色彩を組み合わせた絢爛豪華な織物を意味する言葉でしたが、後に古代の人々により創出された、八節の動作を組み合わせた導引術を指すようになりました。北宋の洪邁(1123-1202)の『夷堅志』にもこの名称が見られますが、詳細な絵図と解説文が初めて現れたのが16世紀以降の『赤鳳髓』などの養生書で、具体的な動作の説明や、わかりやすくまとめた解説文、絵図などが含まれます。