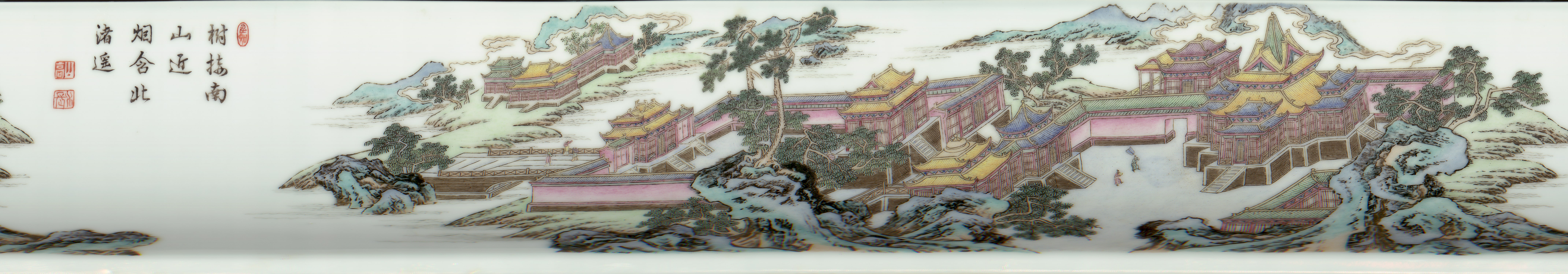皇家ならではの設計と職人の工芸技術
康熙朝と雍正朝(1662-1735)で成し遂げた発展の軌跡を継承しつつ、乾隆朝(1736-1795)の琺瑯彩磁器はそれまでの様式が意図的に刷新されました。器形や紋様、伝世の経緯から見ると、「詩境と画意」、「新しい装飾模様」、「収納とコレクション」─三つの面から理解することができます。
1組目の「詩境と画意」では、雍正朝(1723-1735)から継承され、皇家だけに使用が許されていた様式の作品を展示します。碗や盤(皿)、瓶などには皇家の職人が筆を揮った、絵画のような模様が描かれています。どの作品にも前人の詩句が書いてあり、細緻な絵図と閒章の組み合わせになっています。前朝から受け継がれた作風も見られますが、細部は意図的に変更されています。それに対して、景徳鎮の陶工が手がけた洋彩磁器は皇帝の詩文が古典作品に取って代わり、詩文と絵が対応する形となっており、この時代ならではの風格が強く感じられます。2組目の「新しい装飾模様」では、乾隆朝で創出された新しい装飾模様をご覧いただきます。洋彩と琺瑯彩に共通する様式がある中で、それぞれが独自の発展を遂げているのが特色です。3組目の「収納とコレクション」では、現存する木製の収納箱から、乾隆帝(1736-1795)が行った清朝宮廷旧蔵品の点検及び整理のほか、18世紀に収納された洋彩と琺瑯彩磁器を分類整理した後、各作品に名前を与えて包装を行った、それらの出来事を当時に遡ってご紹介します。
詩境と画意
前人の詩句が装飾模様の主題を示しています。また、手描きの印章も「寿如山高水長」や「太平盛世」など、吉祥の意味を伝えています。この点がこれらの作品の最大の特色です。公文書によれば、宮廷で定めた共作の取り決めにより、新しい作品を制作する時は、絵図や題句から年款の書写まで、全ての作業にそれを専門に行う人員がいたそうです。題句に注目してみると、その多くが前朝で使われたもので、新たに選出された詩作はごく少数です。しかし、模様の配置や扱い方に関しては、画面の豊かさにより重きが置かれ、主題との関連性や器の内外を問わず、宮廷の工匠たちは思いもよらない細かな工夫によって、琺瑯彩磁器の装飾模様に賑わいや、活力溢れる雰囲気をかもし出そうとしたのです。
様々な様式の瓶
画琺瑯工芸の研究開発から焼成までは、207陳列室の展示作品が伝えてくれる物語のように、実験の段階を経てから、ようやく完成に至りました。しかし、展示作品をご覧になれば、この点もまたおわかりいただけるでしょう。器形の大半は盤(皿)と碗で、比較的多数の瓶が登場したのは乾隆朝(1736-1795)になってからのことです。このような変化が生じた要因は複数あったと思われますが、公文書には皇帝が様々な瓶の制作を幾度も求めたことが記されています。しかも、琺瑯を焼くように指定されたそうです。この出来事は、このような変化を導いた要因の一つとみなすことができるでしょう。
対の作品
乾隆帝は対になった作品の制作を求め、2点1組での収蔵を望んだため、乾隆年製の琺瑯彩磁器は模様の配置や構図など、二つの作品が呼応する点も特色となっています。詩句が書かれた磁器の盤(皿)を例に見てみましょう。一つは模様が左側に寄せてあり、もう一つは右側にあります。装飾模様も変化の途上にあるようで、対の作品を制作する上での工夫が感じられます。
新たに選出された詩文
雍正朝(1723-1735)で選録された題画詩は、康熙帝(1662-1722)の命により編纂された詩集の詩文から主に取られています。そのため、康熙帝による文化政策の継続という観点から見ると、雍正朝で制作された琺瑯彩磁器は基本的に康熙朝以来の同一線上にあるとみなすことができます。乾隆朝(1736-1795)では、新しい皇帝が新鮮味や変化を求め、従来の規定を変更して、新たな作品を創出しようとしました。しかし、伝世作品を見ると、詩句の選出に関しては、雍正朝では見られなかった題句が幾つか登場していますが、基本的には康熙詩集の範疇にあります。
人物に注目
この胆瓶から皇家の工匠が描いた模様を読み解いてみましょう。底の近くに描かれた岸辺には長衫(丈の長い服)をまとった高士が三人いて、これから川を渡ろうとしています。川の対岸には長い竿を繰りながら、ゆっくりと進んで来る船頭の姿が見えます。続いては、山林の入口に注目してみましょう。一人の高士が杖をつきながら歩いています。その後ろには琴や書物を抱えた侍童がいて、二人は友人の家を訪れるところのようです。三つ目の場面では、黄昏時だからでしょうか、今日も一日中働いた樵が、柴を担いで山林から出てきました。樵の歩調に合わせて上方に向かうと、窓にもたれて景色を眺めている人物が目に入ります。
紅山水
赤い琺瑯料で描かれた風景や人物画を紅山水と言います。康熙朝閩浙総督覚羅満保(1673-1725)は康熙帝から「法瑯白地紅山水鼻煙壺」を賜っています。このことから、康熙朝の頃すでに紅山水の紋様が出現していたことがわかります。このような西洋銅胎琺瑯器を由来とする紅彩絵画は、乾隆帝からも重んじられました。乾隆3年(1738)、銅胎紅山水鼻煙壺を見た乾隆帝が、実に精妙で好ましい絵図だと称賛したため、皇家作坊の職人も磁胎作品に取り入れるようになったのです。
仙山楼閣
16世紀以来、漢唐宮殿は蘇州の作坊(工房)が手がける名画の題材として大切なものになっていました。それに対して、乾隆朝の琺瑯彩磁器に登場した仙山楼閣図は、雍正年間の単色装飾模様に色付けして、より趣のある情景としたもので、新しく創出された紋様とみなすことができます。折帯皺法による白雲が樹木の生い茂る青山を縫うように描かれており、地面は青々とした草に覆われ、岸辺にはせせらぎの音が響いています。中ほどには建設中の高台や宮殿群が連なっており、紅い塀と色とりどりの屋根瓦、巨石と樹木によって、清らかで脱俗的な雰囲気が際立っています。造辦処の公文書によれば、このような様式の図案は遅くとも乾隆5年(1740)には、すでに完成していたそうです。
宮廷所蔵の絵図を用いた図案
こちらにある一対の磁瓶は、造形が古画に描かれた双陸棋に似ているため、双陸瓶と称されます。地の色は全体に淡い水色の釉料が施され、桃の花の配置と薄紅色が、蒋廷錫(1669-1732)『群芳擷秀』冊の「碧桃」を連想させます。この点から、皇帝と督陶官による管理の下、御窯廠で生産されていた洋彩磁器の図案に、宮廷所蔵の絵図が用いられた可能性も考えられます。
乾隆帝御製詩
乾隆帝は「余暇の楽しみは詩を書くこと」と述べていますが、本当でしょうか。乾隆帝は生涯を通して4万首を超える詩を書きました。計算すると、毎日少なくとも1首以上の詩を書いたことになります。この大量の詩作は詩集として出版したり、古代の器物に刻したりしたほか、一部は装飾模様として用いられ、乾隆朝官窯の作品に書き込まれました。こちらの展示作品のように、景徳鎮で制作された洋彩の小品には御製詩が書いてあります。内容は一稿両用の題画詩で、その時々の思いや、橋を渡ってから見えた風景など、実に様々です。
転足碗
一般的な碗の底には机に直接触れる高台が付いています。この部分を中国語では、陶磁器の専門用語で「圏足」と言い、この圏足の上で器身が回転する碗を「転足碗」と言います。督陶官が乾隆帝に送った奏摺(簽文)を読むと、当時の状況が理解できます。乾隆帝が康熙朝と雍正朝の官窯とは別の新しい作品を生み出そうと注力していた中、唐英もかなりの重圧を感じていたはずですが、皇帝の要望に従って研究開発を続けなければなりませんでした。そしてついに乾隆8年(1744)、透かしのある二重の套瓶や回転機能を付けた磁器─計9種を宮廷に納めたのです。翌年(1745)の造辦処の公文書にも「洋彩山水詩意連架大靶碗」1点が記録されています。この二つの資料は時期が非常に近いことから、この種の作品の創作が試みられた時期と、その試みが成功したと考えられる年が窺えます。