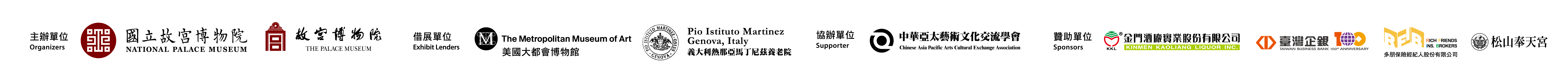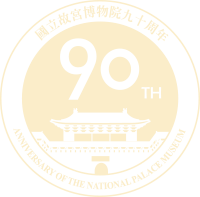郎世寧(ジュゼッペ・カスティリオーネ/Giuseppe Castiglione)の花鳥画は多種多様で、中国伝統の画法とは描き方が異なります。作中に描かれた景物の多くは色面で形が表され、伝統絵画のように輪郭線を描いた作品はほとんどありません。故宮所蔵の「画仙萼長春」冊はその典型だと言えるでしょう。この冊は絹画十六開からなり、その内の八開は花卉を主題としています。残りの八開には花卉と鳥が描かれており、最後に「臣郎世寧恭画」という署名があります。写生によって究められた花鳥の造型や鮮麗な色遣いは、清朝宮廷画院で独自の画風を築いた郎世寧の代表作というにふさわしいものです。
西洋の写生技術を修得した郎世寧の確かな画力は、この冊の至るところに見て取れます。例えば、ボタンの花弁に施された細やかなグラデーションや色面の丁寧な処理、ハクモクレンやケイトウの反り返った花弁に見られる濃淡の変化、細部まで表現された明暗の違いなど、光源へのこだわりが強く感じられます。溌剌とした野鳥達の生き生きとした目の多くは白粉の点染で描かれています。山石や樹木の枝幹は高所から降り注ぐ光で凹凸が立体的に表現されています。清朝宮廷の磁器工芸にも、画冊に見られる各種の花卉や鳥類の描写とよく似た表現があり、宮廷で用いた画稿の流用や使用状況が窺えます。
清 郎世寧
仙萼長春
- 冊 16開 絹本着色
- 各縱33.3cm 橫27.8cm
十六開からなるこの冊は、ボタン、モモ、シャクヤク、ハナカイドウとモクレン、ヒナゲシ、シャガ、ロサ・キネンシスとボタン、セキチク、サクランボ、ケシ、ライラック、ユリとボタン、アサガオと竹、ハスとクワイ、マメ科の花とアワの穂、ケイトウ、キクを描いたもので、その内の八開には野鳥も合わせて描かれている。この冊の内容は『石渠宝笈三編』所収の「郎世寧画花卉冊」と一致する。対幅(見開き頁の一方)は全て空白となっており、最後の一開に宋体の落款「臣郎世寧恭画」がある。画風の特色から推測するに、雍正朝時代に制作した花鳥画の佳作であろう。全ての作品に精緻な着色が施され、構図に新鮮味がある。特に野鳥の姿にはそれまでの伝統を超える表現が見られ、この点は西洋の遠近法による大きな成果だと言えよう。多くの箇所に光による明暗の変化がはっきりと示されており、白い顔料で高所から差す光を表現する技巧もしばしば用いられている。全作品の画風が、郎世寧の雍正朝前期の画風に関連することを強く示している。
清 雍正
琺瑯彩磁柳燕図碗
- 高さ7.4cm 底径6.7cm 口径16.0cm
大きく開いた口、丸みのある深さい見込み、高台は低い。全体に白い釉が施されている。内側は無紋で、外側のほぼ全体に柳とツバメの絵が描かれている。一方の面に墨で書かれた題「玉剪穿花過、霓賞帶月帰」があり、引首には朱で「佳麗」、句末に「四時」と「長春」の二印がある。高台の底に青の宋体4文字の落款「雍正年製」があり、周囲は二重の線で囲まれている。題句の内容は明代の申時行「応制題扇」所収の詩で、柳の間を縫うようにして舞い飛ぶツバメの画意を形容している。雍正帝は画琺瑯の装飾模様をかなり重視し、西洋人宣教師の郎世寧とその弟子である林朝楷に、立て続けに命を下しただけでなく、画家の賀金崑や戴桓、湯振基、鄒文玉、譚栄などのほか、画状元の唐岱などにも画琺瑯器の絵模様を描くように命じている。それと同時に宮廷で制作する器物は「内廷恭造式様」でなければならぬとの規定を宣布した。白い釉を施した碗や盤に題句と描印を入れ、書画に対応する模様を創造した点は、康熙朝とは趣を異にする新しい風格だと筆者は考える。この作品には、枝にとまる2羽のツバメが互いにさえずる様子が描かれている。その表情は生き生きとして愛らしい。郎世寧の「画仙萼長春」冊に見られる桃の花の描き方に近く、画琺瑯の装飾模様と院体画構図の密接な関わりが具体的に示されている。
清 乾隆
琺瑯彩磁紅地花卉魚藻紋碗
- 高さ2.8cm 口径5.1cm 底径1.8cm
大きく開いた口、玉縁は細い。丸みのある深さい見込み、高台は低い。内側は白釉が施されており、底に金魚と水草の絵模様がある。外側は赤い地に雪の結晶のような方形の紋様が刻まれているほか、美しく華やかな草花の模様二つで装飾されている。口縁と高台の縁は白い筋が残され、高台の底に青の宋体4文字の落款「乾隆年製」がある。『活計档』の記録から、全体に模様を施した上に、細やかな筆遣いで丹念に描かれた西洋風の花やセキチクなどで装飾する手法は、乾隆帝がこよなく愛した「錦上添花」の影響を強く受けたものだとわかる。この模様が初めて登場したのは、乾隆5年(1740)で、碗の内側に見られる金魚と水草の模様は乾隆8年(1743)にすでに登録された上、記載されている。2種類の模様の組み合わせは、この作品の生産量の上限を間接的に示している。雍正朝の詩画に対応する様式に対して、「錦上添花」は乾隆朝で新たに創作された装飾模様と見なすことができる。郎世寧の「画魚藻」と、この碗に描かれた金魚や水草は異なるが、郎世寧も乾隆14年(1749)に皇帝の勅命で「通景画」に金魚と水槽の描き入れており、「通景画」の写実的な特色を考えると、乾隆朝の洋彩や琺瑯彩磁器にしばしば登場する金魚と水草の模様もまた宮廷の西洋趣味と密接な関わりがあった可能性は排除できない。興味深さいのは、乾隆10年(1745)から、金魚碗や盤(皿)もまたオランダ東インド会社にとって購入必須の品になっていた点である。沈没船「南京号」(The Geldermalsen)から引き上げられた金魚碗や盤が正にこの金魚と水草模様のある食器類なのである。このことは、乾隆時代の官窯で作られた金魚と水草の模様が、官民の境界を越えて広く流行し、宮廷だけでなく各地方にも流通していたことを示しているだけではない。金魚模様の磁器が主に西洋の市場に向けて出荷されていたのは、それに含まれる西洋趣味的な要素を間接的に示していると思われる。
清 乾隆
銅胎画琺瑯西洋人物牧羊図碟
- 高さ0.8cm 口径10.1cm
口縁は丸く、内側にやや折れており、金色の縁が盛り上がっている。浅い皿で底も円形、高台の縁はわずかに外側に広がっている。縁に沿って巻草紋が金泥で描かれており、その間を飾る小さな天使5人はそれぞれ青、赤、黄、紫色のリボンを持っている。中心に描かれた西洋風の牧羊図の周囲は縄の模様で飾られている。外側は黒い琺瑯料(エナメル)の地に金泥巻草紋が二重に描かれている。底は白と黒のグラデーションになっており、西洋風の図案や赤いコウモリの模様で装飾されている。底の中心に描かれた花の中に「乾隆年製」4文字の宋体落款(上下2段左右2行)がある。収納用の木匣もあり、蓋に「乾隆年製銅胎画琺瑯西洋人物大小碟二件」と記されていることから、似たようなモチーフを扱った「円碟」(丸い小皿)がもう1点この匣に収められていたことが知れる。この名称から、道光15年(1835)の『琺瑯金銀銅胎陳設档案』に記載された作品であることもわかる。黒地に金泥と縄の装飾模様、底の図案など、全てが16世紀フランスのリモージュ(Limoges)の琺瑯器に見られる装飾様式の模倣である。その中に加えられたコウモリと霊芝が、この作品に中西融合という特色を与えている。日本の永青文庫に収蔵されている「パリスの審判」(The judgement of Paris)の絵図がある琺瑯彩磁器と全く同じモチーフの装飾がリモージュの琺瑯器にあることからも、こうした西洋風の図案の流行は雍正朝を経て一旦沈静化したが、乾隆朝で再び大流行したように思われる。この流動的な変化は、或いは乾隆帝が西洋文化を受け入れたことと深さい関わりがあるのかもしれない。