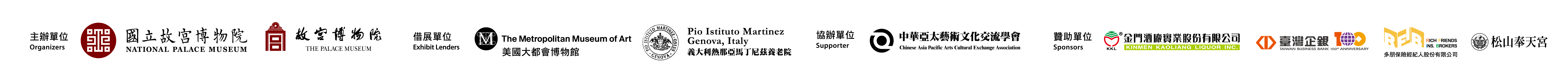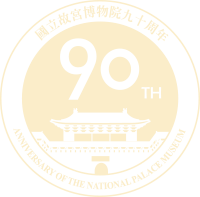1688年7月19日にイタリアのミラノで誕生した郎世寧(ジュゼッペ・カスティリオーネ/Giuseppe Castiglione,1688-1766)は、幼少の頃から絵画を学んでいました。19歳(1707)の時にジェノヴァ(Genoa)でイエズス会士となり、1709年にポルトガルのリスボンへ移りました。その後、1714年にローマ教皇庁により中国(清国)に派遣され、1715年(康熙54年)に澳門(マカオ)に到着しました。この度の特別展で展示されるイタリアのPio Istituto Martinez養老院所蔵の未公開作品は、ジェノバで制作した作品だとされています。来華前にヨーロッパで制作した絵画の実例であり、郎世寧の西洋美術本来の作風がご覧になれます。
郎世寧が来華したばかりの頃─康熙、雍正時代に制作した絵画作品はそれほど多くありませんが、中西融合とも言える画風は多元的で精彩に富んでいます。郎世寧は中華的な題材を取り入れつつ、景物を形作る陰影や背景の奥行きなどで伝統的な中国画とは異なる新しい表現を生み出しました。その一方で、西洋画の技法を中国伝統の扇面に用いることもあり、彩色磁器の絵模様にも郎世寧との関連が見て取れるなど、内廷による美術品の制作で郎世寧が果たした様々な役割を知ることができます。
清 郎世寧
聚瑞図
- 軸 絹本着色
- 縦173cm 横86.1cm
青磁の瓶に生けられた蓮の花や穀物の穂など、吉祥を意味する植物が描かれている。聖人による治世を象徴する宋元以来の画題である。款題は清宮廷で印刷用に用いた「宋字」で書かれている。制作年は雍正元年(1723)、郎世寧最早期の作品である。視点が画幅の三分の二の高さに水平に置かれているため、瓶の口の内側が見える。光沢を放つ瓶の艶やかな質感が白い顔料で表現されており、より立体感に見える。植物は色彩で立体的な凹凸が表現されているだけでなく、明暗の違いも生かされている。全体に丹念かつ精緻な着色が施され、物象そのものから光が発せられているかのような質感がある。中国的なモチーフを扱いながら西洋画法を駆使した見事な作品となっている。画中の青磁瓶は本院所蔵「雍正倣汝釉青磁弦紋瓶」の体裁に近い。
清 郎世寧
花底仙尨
- 軸 絹本着色
- 縱123.2cm 橫61.9cm
満開の桃の花が咲き誇る庭園の一角と赤褐色の子犬が描かれている。ごつごつとした老木から桃の花と枝葉が伸び、根元は複雑に絡み、しっかりと地面に根を張っている。その根元から生える数本の細い枝にもつぼみがあり、老木の生命力の強さが感じられる。その背後に聳える高大な湖石の奇妙な形状も老木に呼応している。愛らしい子犬の動きはよく観察されている。絵の中で静止している子犬に微かな躍動感があり、何か他の事に気を取られているようで、立ち止まってそちらの方を振り向いている。郎世寧は精緻かつ的確な手法で動物を描き、立体感はもちろんのこと、毛のつやまでも表現している。本物そっくりの外観と内面まで丁寧に描写する手法は、これ以降、郎世寧の動物画に不可欠の要素となった。この作品に年款はないが、清朝の公文書によると、雍正5年(1727)2月に郎世寧が「者爾得」(満州語でナツメ色の意)の子犬の絵を手直ししたとの記録があり、或いはこの作品のことかもしれない。
清 郎世寧
画山水 軸
- 軸 絹本着色
- 縱143.2cm 橫89.1cm
連なり重なる山々の間を雲霧がたなびき、家屋や東屋、小さな橋が見え隠れしている。郎世寧は皺擦法と鉤勒法、素描に似た点法を取り入れ、物象ごとに異なる質感を表現している。樹木の葉は乾湿濃淡の微妙な変化で表され、丹念に施された着色は明るく清らかである。朦朧と浮かびあがる雲霧が画面に奥行きを与えている。
郎世寧は伝統的な文人画を学んだ経験もある。その対象は王原祁(1642-1715)の弟子で宮廷画家の唐岱(1673-1752以降)だった。山頭の造型や雑木の配置、皺法、苔点などに唐岱の筆法を学んだ痕跡が見られる。この二人は勅命により幾度も合作を経験した。こうした関係によって清代初頭の画壇で「正統」な画風が継承されたのである。
清 郎世寧
四季花卉棋盤
- 木胎棋盤 絹本着色
- 縱25.7cm 橫26cm
棋盤(将棋盤)の裏に貼られた絹画に、水辺に咲く花々が描かれている。ウメやキク、ハス、イチハツ、ホンカイドウ、ボタン、キキョウ、シュウカイドウなど、花期の異なる花々が一斉に咲き揃い、枝にとまる2羽の小鳥が語らうようにさえずっている。この棋盤は折り畳むことができる。組み合わされた盤面はそれぞれが独立した画面として見ることもでき、このあたりにも匠の心が感じられる。右上にある梁詩正(1697-1763)の題句「四序繁英一局中」、「筆端疑有迴文様」も棋盤の画意に似合わしい。郎世寧の作品にこのような小品は少ない。断続的なタッチで描かれた斜面や水面に映るハスの茎を見るに、早期の画風だと考えられるが、落款に「臣」の字がないのを見ると、皇帝に仕えただけではなく、多種多様な作品を手がけていたことが窺える。
清 郎世寧、張若靄
書画合璧竹骨摺扇
- 摺扇 紙本着色
- 縱28cm
本院所蔵品中で唯一、郎世寧が手がけた画扇である。墨箋に鮮やかな色彩で植物や昆虫などの小景が描かれている。岩の上にはキリギリスがいて、ミツバチがタンポポの蜜を集めている。花と茎に当たる光が光源の位置を示している。丁寧な着色による光沢で昆虫の量感が表現されており、キリギリスの身体を覆う細かな毛や触覚、岩の陰影などもうっすらと見て取れる。反対の面には張若靄の書「唐人月儀帖(二、三月)」があり、画中の季節に呼応しているようである。おそらく早期の作品で、三次元の物象の特徴が写実的に描かれており、伝統的な草虫画に新味を与えている。東アジア発祥の摺扇に西洋人が絵を描き入れた、かなり特別な作品だと言える。
明 宣德
青花牽牛花紋折方瓶
- 高13.8cm 口徑5.8cm 足徑7.2cm 深10.6cm
細く縁取られた丸い口、首は長く、両側に龍の頭を象った獣耳がついている。胴は方形で、斜めに削られた上下四隅は三角形になっている。高台の足は外側に開き、白い胎が縁からのぞいている。獣耳は全体にコバルト釉が施され、口と高台にも青い線が引いてある。白釉の地に青で複雑に絡む牽牛花(アサガオの一種)が瓶全体に描かれている。底に青花6文字の落款「大明宣徳年製」があり、その周囲は二重線で囲まれている。郎世寧の画作「画瓶花図」を見ると、宣徳時代の磁器瓶が清朝宮廷に持ち込まれ、花器として使用されていたことがわかる。「画瓶花図」に描かれている青花磁器の瓶は、かなり早くから研究者により宣徳朝の磁器だと指摘されていたが、画中の瓶がどれなのかは不明のままだった。本院と大英博物館の収蔵品には、細部に若干の違いが認められ、郎世寧の画作に描かれた瓶がどちらなのかを特定するのは、現時点では困難である。「画瓶花図」のほか、大英博物館とヴィクトリア&アルバート博物館収蔵の「古玩図」巻中にもよく似た青花折方瓶が描かれている。絵画に磁器を描き入れるのが、18世紀に流行していたことを反映している。
清 康熙
宜興胎画琺瑯花果茶碗
- 高5.7cm 口徑11.2cm 足徑4.5cm
大きく開いた口、丸みのある深さい見込み、高台は低い。器の色と形に合わせて口と高台の縁に一本の線が刻されている。内側は無紋だが、外側には紫砂の素地に桃の実やライチー、シトロン、ビワ、カキ、ザクロ、ブドウ、シログワイ、サクランボなどの果物の模様が描かれており、その隙間を埋めるように、ランやロサ・キネンシス(バラの一種)、ヒナギクなどの花々が彩りを添えている。底に2行4文字の黄色の落款「康熙御製」がある。この器はかつて端凝殿に収蔵されていた。『清宮物品点査報告』を見ると、道光15年『琺瑯玻璃宜興磁胎陳設档案』(1835)の品目の一つとして登録されていたことがわかり、そこから、乾隆帝が匣に収めるよう命じた際に「宜興胎画琺瑯三果花茶碗」と命名されたことが知れる。全体に丁寧な暈染(ぼかし)で花と果物の模様が描かれている。題材といい、筆法といい、伝統的な中国磁器にはあまり見られないもので、西洋の静物画を連想させる。郎世寧の「画午瑞図」に描かれた果物を盛った器も西洋の静物写生画によく似ており、この種の絵図は宣教師を通して清朝宮廷にもたらされたのかもしれない。しかし、全体に花と果物が描かれた、このような容器は他に見当たらず、西洋の静物画と完全に一致するとも言えないため、新たな紋様を試作したものだと思われる。興味深さいのは、康熙から雍正、乾隆三朝の琺瑯彩磁器にも青紫色のヒナギクがしばしば現れ、郎世寧の「画万寿長春図」にも画面のアクセントにこの花が登場する点である。
清 康熙
銅胎画琺瑯花果紋盒
- 高6.1cm 口徑15cm 底徑5cm
扁平な丸い盒。蓋と器の凹凸がぴったりと重なるようになっている。蓋と器の縁、高台の縁は胎に鍍金されている。内側は無紋で、水色の琺瑯が施されている。外側は白く塗られ、桃の実やシトロン、ザクロなどが描かれており、果物の間を埋めるボタンやロサ・キネンシス(バラの一種)、ヒナギクが華やかさを添えている。花々と果物が交錯しながら互いに映え、それが独特の趣となっている。高台の底に青い宋体4文字の落款「康熙御製」があり、周囲は二重線で囲まれている。蓋には没骨法でシトロンが描かれている。色に濃淡の変化があり、皮の質感は点描で表現されている。線描で描かれた花葉の模様と二つのシトロンが鮮明な対比をなしている。部分的に見られる西洋の筆法が、画琺瑯の技術に含まれる西洋的な要素を示している。
清 雍正
倣汝釉青磁弦紋瓶
- 高44.1cm 口徑11.2cm 底徑16.5cm
丸い口は大きく、首は細く長い。丸みのある大きな胴、厚い胎は重量感がある。底は平らで高台は低い。高台の両側に方形の穴が一つずつ開けられている。全体に汝釉に似せた青色の釉が施されている。焼成後は灰色がかった水色となり、釉の表面は細かな貫入で覆われている。均整の取れた高台の縁は胎がのぞき、そこに褐色の「護胎汁」が塗られており、宋代磁器特有の濃色の胎骨となっている。底に青花6文字の篆款「大清雍正年製」がある。首から肩、胴にかけて6本の弦紋で装飾されている。河南省宝豊県清涼寺北宋汝窯窯跡と浙江省杭州市南宋老虎洞窯跡で出土した標本に器形のよく似た瓶がある。この作品は釉の色が薄く、高台の底が意図的に濃く塗られていることから、雍正官窯による倣宋磁器なのは明らかであり、官窯と汝窯─両者の作法が統合されている。雍正元年(1723)に完成した郎世寧「聚瑞図」と対照すると、画中に描かれた磁器が雍正時代の倣官作品であることがわかる。
清 乾隆
炉鈞釉胆瓶
- 高40.5cm 口徑5.2cm 底徑12.2cm
直線的な口、長い首、なだらかな肩、梨形の胴、高台は低い。全体に炉鈞釉が施されている。赤紫色の釉に水色が浮かび、青みがかった乳白色とナスの花色の斑模様が入っている。焼成中に自然に流れた釉が混じりあって生じた紋様である。底に赭汁が塗られ、そこに月白釉が施されている。中心に6文字の篆款「大清乾隆年製」がある。胎がのぞく高台の縁にも赭汁が塗られている。こうした模様のような釉彩が雍正時代に誕生した炉鈞釉の特色である。この色鮮やかな作品の独特な釉色は、乾隆朝の『活計档』に「先に精錬するべし」と記されている「鈞釉磁面」なのかもしれない。北京故宮博物院に器形がほぼ等しく、金彩の御製詩で装飾された磁器瓶が一点収蔵されている。御製詩は皇帝御用の象徴であることから、一見すると非常に伝統的なこの胆瓶の器形は、郎世寧が乾隆13年(1748)に形を変えて絵にした双耳鈞釉瓶の様式に呼応するものかもしれない。