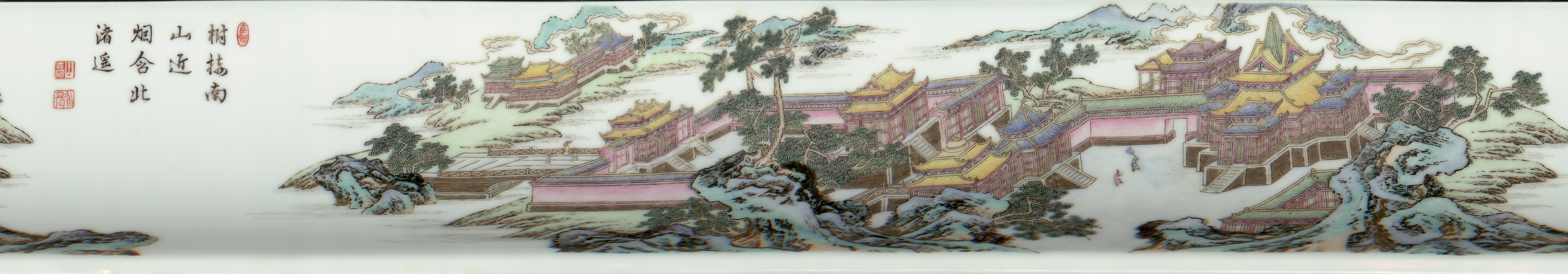彩料の相乗効果
「双彩」とは、洋彩と琺瑯彩─2種類の彩磁を指します。督陶官唐英(1682-1756)によれば、洋彩は御窯廠で制作された、琺瑯彩磁の装飾紋様を模倣した製品のことです。洋彩の生産開始は乾隆朝(1736-1795)からではありませんが、乾隆帝は「洋彩洋花」図案の磁器を制作するよう特に指示していたほか、細緻かつ精密な洋彩磁器の幾つかを「頭等」に分類するなど、洋彩にも注目せずにはいられません。展示作品の中に、雍正朝琺瑯彩磁の風格を受け継ぐ作品が1組ありますので、気をつけてご覧になってみてください。器表の詩画の配置には前朝の名残りが見て取れますが、細部にもすでに変化が生じています。もう1組の作品は、乾隆御製詩を中心に新しく創作された洋彩です。
督陶官:江西省景徳鎮に派遣され、御窯廠での生産を管理した下級官吏。
詩意・画境
呼応する詩画を紋飾の主題としており、その前後にある閑章が紋様の含意を伝えてくれます。清雍正帝(1723-1735)が命じて推進した、宮廷限定の様式です。これによく似た構図は乾隆朝で制作された琺瑯彩磁にも見られます。本院所蔵品を例に挙げると、およそ19作の題句に雍正朝で選ばれた詩文がそのまま用いられています。とはいえ、紋様の表現法を見ると、余白が徐々に減らされているほか、細部の描写が重んじられているなどの特色も見て取れます。
- 清 雍正 琺瑯彩青山水盤
- 清 乾隆 琺瑯彩寿山福海碗
新たに選出された詩文
雍正朝(1723-1735)で選出された題画詩は、主に康熙帝(1662-1722)の命により編纂された詩集から取られています。そのため、康熙帝による文化政策の継続という角度から見ると、雍正朝で制作された琺瑯彩磁は、基本的には康熙朝と同一の流れにあるものとみなせます。乾隆朝(1736-95)では、新しい皇帝が新味や変化を求め、それまでの規定を変更して、新たな作品を創作しようとしました。しかし、伝世品を見ると、詩文の選出に関しては、雍正朝では見られなかった題句が幾つか現れましたが、ほぼ康熙詩集の範疇にありました。
- 清 乾隆 琺瑯彩灯火昇平碗
- 清 乾隆 琺瑯彩赭墨蘆雁酒鍾
乾隆帝御製詩
乾隆帝は自分の趣味は詩作だと言いましたが、本当でしょうか?乾隆帝は4万首を超える詩を創作しました。計算してみると、1日に少なくとも1首以上を書いたことになります。この大量の詩文で詩集を出版したり、古器に彫刻したりしたほか、装飾模様の一部として使ったり、乾隆朝の官窯作品に書き込んだりもしました。展示作品に見られる通り、景徳鎮で制作された洋彩の小品には御製詩が書いてあり、一つで両用の題画詩となっています。四季折々の情趣も表現されており、絵の中の橋を渡ると、その向こうに様々な風景が見えてきます。
- 清 乾隆 洋彩山水人物観音瓶
紅山水
赤い琺瑯料で描かれた風景や人物画を紅山水と言います。康熙朝閩浙総督覚羅満保(1673-1725)は康熙帝から「法瑯白地紅山水鼻煙壺」を賜っています。このことから、康熙朝の頃すでに紅山水の紋様が出現していたことがわかります。このような西洋銅胎琺瑯器を由来とする紅彩絵画は、乾隆帝からも重んじられました。乾隆3年(1738)、銅胎紅山水鼻煙壺を見た乾隆帝が、実に精妙で好ましい絵図だと称賛した影響で、皇家工房の職人もそれを磁胎作品に取り入れるようになったのです。
- 清 乾隆 琺瑯彩緑地剔花紅山水碟
- 清 乾隆 琺瑯彩緑地福山寿海紅山水盤
仙山楼閣
16世紀以来、蘇州の工房では、漢唐宮殿建築が名画の重要な題材の一つになっていたようです。それに対して、乾隆朝の琺瑯彩磁に描かれた仙山楼閣の絵は、雍正時代の単色調の絵模様に彩色し、情景を添えた新しい紋様でした。樹木が鬱蒼と茂る青山に折帯皴法による白雲がたなびき、地面は青々とした草で覆われ、川のせせらぎが聞こえてくるようです。その間には、遠方まで連なる宮殿群があり、赤い塀や色瓦、巨石、樹木に彩られて、神秘的な雰囲気をかもし出しています。造辦処の公文書によれば、遅くとも乾隆5年(1740)には、このような様式が完成していたと考えられます。
- 清 乾隆 琺瑯彩山水楼閣碗
転足碗
一般的な碗の底には、机に直接触れる高台が付いています。その部分を陶磁器の専門用語で「圏足」と言い、圏足の上にある器身を回転させられる碗を「転足碗」と言います。督陶官が乾隆帝に進上した奏摺(上奏文)から当時の状況が理解できます。乾隆帝は康熙朝と雍正朝の官窯とは違う新しい作品の制作に注力していました。そうした状況の中で、唐英にも重圧がありましたが、皇帝の諭旨に随い、研究開発を進めるしかありませんでした。そしてついに乾隆8年(1743)、唐英は精巧な透かしのある二層套瓶と器身が回転する仕組みの磁器─計9点を皇帝に進上しました。その翌年(1744)の造辦処の档案(公文書)にも「洋彩山水詩意連架大靶碗」1点が記載されています。この2種類は時間的にかなり近く、この種類の作品の創出及び完成時期が推測できます。
- 清 乾隆 洋彩漁村行楽図転足碗