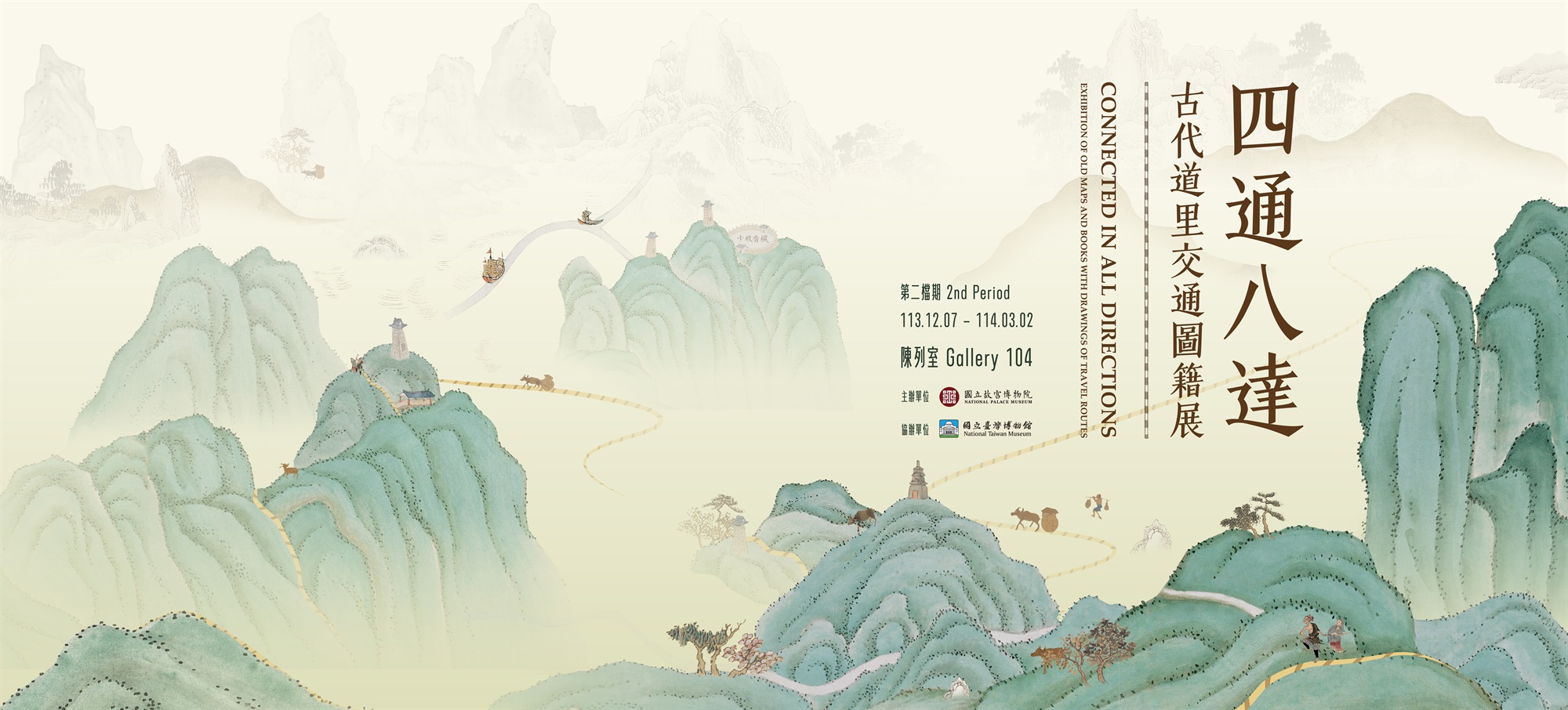国境警備の道
古代の中央政府は国境地帯の平和と安定を守り、主権を知らしめるために、定期または不定期で人員を派遣して国境地帯の巡察にあたらせていました。そのため、「巡辺図」と言われる地図が登場したのです。明~清代(14世紀後期~20世紀初期)、国境付近の揉め事の多くは北方からやって来たので、巡辺図もそれらの地域に集中していました。例えば、黒龍江档案館所蔵の「黒龍江地区巡辺路線図」や故宮所蔵の「吉林九河図」(平圖021457)などがあります。展示中の「辺防図」は北方の防衛や警備についてではなく、清代の西南方面の国境付近が描写されています。広西省帰順州から始まり、栄労、湖潤寨を経て東南に向かい、下雷土州に至る間のベトナムとの国境付近一帯が描かれています。この図を見ると、この二国間は「牆」と「濠」、「柵」を境界としており、国境線警備のための隘口や兵卡、汛堡、村落も一つ一つ描き込まれています。そして、これら国境防衛の要衝を繋ぐのが、大山を蛇行する赤い点線で示された道路です。この図が何か特定の活動と関連があったか否かはわかりませんが、「隴邦汛」の下に注釈があり、「隴邦は左営汛地の管理下にあり、隘卡は栄労隘から始まり咘透卡で終わる。合計8隘9卡あり、規定の日に巡察を行う。」と記されています。「巡査」(巡察)という文字から推測すると、「巡辺」(国境警備)と無関係ではないはずです。